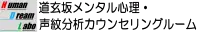現代において「仕事がつらい」と感じる人は少なくない。長時間労働や成果主義の拡大、リモートワークによるオン・オフの境界の曖昧化など、働く環境はかつてより柔軟さを増す一方で、新たな負担も生み出している。
第一に、過剰な労働時間が心身を疲弊させている。技術の進歩によって効率化が進んだにもかかわらず、仕事量はむしろ増え、常に「もっと成果を出さなければならない」というプレッシャーが伴う。これが慢性的な疲労やストレスを引き起こし、うつ症状や燃え尽き症候群へとつながるケースも多い。
第二に、人間関係や組織文化による圧力も大きい。職場でのハラスメントや、暗黙の同調圧力、評価制度の不透明さなどが「自分はここに居場所がない」という感覚を強めてしまう。特に現代はSNSを通じて他人の働き方と比較しやすくなり、「自分だけが遅れている」「頑張れていない」という不安が増幅されやすい。
第三に、仕事の意味を見失いやすい時代であることも問題だ。経済合理性が優先される中で、「なぜこの仕事をしているのか」という根源的な問いに答えられないまま、日々のタスクに追われる人が多い。その結果、「働くこと」が生活の支えではなく、むしろ心身を削る要因になってしまう。
こうした状況を改善するためには、組織の制度改革や働き方の柔軟化はもちろんのこと、一人ひとりが「自分にとっての仕事の意味」を再定義し、無理のない範囲で自己表現や休養を取り入れることが求められる。社会全体が「働きすぎを美徳としない」価値観へシフトすることも不可欠だ。